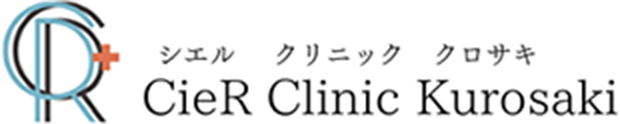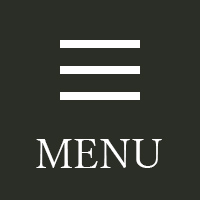酸化マグネシウムのはなし
こんにちは、Phです、今回は便秘薬でよく使われている酸化マグネシウムのお話です
=酸化マグネシウムのはなし=
酸化マグネシウムは古くから制酸剤および緩下剤として使用されている薬です。日本では明治時代から使用されており、1950年には日本薬局方にも収載され、現在、年間推定1000万人の患者さんに使用されています。
酸化マグネシウムは長期投与による習慣性や腸管自体の変化が少なく、慢性便秘の治療に適した薬剤といえます。
=酸化マグネシウムの安全性=
酸化マグネシウムの有害事象として、頻度は低いですが、下痢、腹痛などの消化器障害を発症することがあります。また高マグネシウム血症があります。高マグネシウム血症は長期服用していたり、高齢の患者さん、腎障害のある患者さんに対して注意が必要です。初期症状として、悪心・嘔吐、口渇、血圧低下、徐脈、皮膚潮紅、筋力低下、傾眠症状があります。いつもとなにか違うなあと感じたときは早めに受診してくださいね。
最後に
=栄養素としてのマグネシウムのはなし=
高血圧症の治療の基本は薬の服用と生活習慣の改善ですが、栄養素としてのマグネシウムには血圧の調整する働きがあるのをご存じでしょうか?2016年7月にマグネシウム摂取と血圧の関連性を示す論文が載ったそうです。1日368mgのマグネシウムを3か月間摂取することにより、わずかですが有意に血圧が低下することが示されました。
必須ミネラルであるマグネシウムは血圧調整のほか、筋肉の収縮や神経情報の伝達、体温の調整にも役立っているんですよ
言語聴覚士とは?
こんにちはSTです!
6月になりました♪涼しい春の季節から暑い夏へと変わりつつありますね♪また、今年は早くも梅雨の時期に突入した為、みなさま体調管理には十分ご注意ください!
さて今回は
『言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist)』
についてお話をさせていただきます。
言語聴覚士(以下ST)とは脳梗塞や脳出血といった脳の問題により、上手く話すことができなくなってしまったり(失語症、構音障害)、食事や飲み物を上手に飲み込むことができなくなってしまった方(摂食・嚥下障害)に対してリハビリを実施する専門家です。
その他にも記憶力の低下や注意散漫になってしまった方(高次脳機能障害)に対してのリハビリも実施しております。
近年、高齢化社会が進行すると同時に『摂食・嚥下障害』という問題を抱える方も増え続けております。
単調な生活の中では、食べる事は大きな楽しみの一つです。生活にリズムを作り季節感も感じられ、また食べる事により心理的な満足が得られます。
このことから、人が生きていく上で『食』というのは非常に大切なことなのです。
しかし、飲み込む力は脳の病気や加齢などによって衰えることがあります。周りで食事中によくムセたり、食べにくそうに食事をしている方はいらっしゃいませんか?
もしそのような方がいるとしたら、『誤嚥』を起こす可能性があるかもしれません。
『誤嚥』を起こしてしまうと肺が炎症を起こしてしまい最悪の場合死に至ってしまう場合もある危険な状態になってしまいます。
その為当院のST[は、特に飲み込みが上手くおこなえなくなってしまった方へのリハビリを中心に実施しております。
ご家族様の中で上記の様な症状が現れている場合は気軽にご相談下さいね♪
現在、当院ではPT2名、OT2名、ST1名、リハビリサポートスタッフ2名の計7名が在籍しており、入院、外来でのリハビリを実施しております。
全員がセラピスト経験5年以上の実績は積んだ者なので、みなさまには充実したリハビリテーションをご提供できると思います♪
それでは今月も張り切って頑張りましょう!
痩せ目的の下剤乱用に注意
こんにちは。Phです。
薄着の季節が近づいてきました。同時に体型が気になる季節でもあります。
そこで!!
【痩せ目的の下剤乱用にご注意です】

便秘だから太っている、と思い込んでいる人は多いようで、ダイエット目的で下剤を使用する人がいると聞きます。
果たして、便が出れば体重が減るのでしょうか?残念ながら排便前後の体重変化はせいぜい1kg、通常は数百g程度でしょう。排尿でも300~400g減ります。大便って、けっこう水に浮くんです。ということは水より軽いわけです。
下痢すれば痩せそうな印象があるかもしれません。しかし、刺激性下剤は通常大腸に作用しますが、食物残渣が大腸に達したときには栄養素の吸収はほぼ終わっています。それをいくら出しても痩せたりはできないでしょう・・・
医学的には、正しく痩せるというのは「☆体脂肪を落とすこと☆」です。
体重は体内水分量の影響を受けやすいので、下痢をして脱水になれば一時的には体重は減りますが、それは痩せたとはいえません。
単なる脱水。危険ですね。
皆さん、痩せ目的での下剤乱用には、ご注意です!!
次回は、下剤でよく使用されるお薬、「酸化マグネシウム」についてです。
次回も読んでくださいね(⋈◍>◡<◍)。✧♡
ご報告があります♪
こんにちはSTです!
5月になりました♪今年のゴールデンウィークは最大8日間ほどお休みになる方もいらっしゃるようですが、みなさまはどうお過ごしでしょうか?
当院は、ゴールデンウィーク期間中の外来診療は休診となりますが、入院患者様への対応やリハビリは休むことなく実施しております♪
さて、今回の題材は
『作業療法士(Occupational therapist)』
についてお話をさせていただきます。
作業療法士(以下OT)の基本的な仕事内容は、ベッド上の寝返りや起き上がりなどの基本的な運動や、食事動作、トイレ、着替えなどの日常生活でおこなう運動を上手く出来るように一緒に運動したり、アドバイスをおこなっております。またご家族が患者様の生活のお手伝いをしなければならない場合においても、ご家族の負担が少しでも減るように家族指導も実施しております。
寝たきりの方に対しては、手足の関節が硬くならないようにベッドの上で動かしたり、筋力がなるべく落ちないように運動をおこなっております。その他にも褥瘡(床ずれ)の予防や既に褥瘡が出来ている場合においては、悪化を防ぐ為にベッド上での正しい姿勢の作り方(ポジショニング)を検討しています。
以上がOTについての簡単な説明になります♪
当院では4月から新たなOTが加わり現在2名となりました♪
そこでこのハマブロを通してみなさまへ一言ご挨拶をさせていただきます♪
「こんにちは!4月から浜田病院の一員になりましたOTのHと申します!私の趣味はスポーツ観戦やユーチューブで怖い動画をみたりする事です。年齢は30代、結婚して子供もいます。小さい子供が3人いるので、家で子供の世話をするよりは仕事をしていた方が好きです。
浜田病院のリハビリスタッフはみんな明るく、元気な人ばかりです。訓練室では冗談を言い合いながら患者さんの笑顔を引き出していきたいと考えています!これから一所懸命働きますので宜しくお願いします!」
今回入職されたHさんはOT経験豊富な方であり、みなさまにはより良いリハビリをご提供できると思います!
今月は寒かったり暑かったり気温の変化が大きいですが、体調に気をつけて今月も頑張っていきましょう!!
今年も大人気!! ☆飲む日焼け止め☆
みなさん、こんにちは MedicalSa-noです。
今日は、この時期にオススメのサプリをご紹介します。

飲む日焼け止め(プロテクトエナジー)が、今年も大人気です!!
プロテクトエナジーについてのブログはこちらをチェック
【飲む日焼け止めプロテクトエナジー】
★朝一粒飲むだけで24時間紫外線から守ります★
そして!
ローズマリーやシトラスの自然由来もサプリメントなので安心です。
日に焼ける前の予防はもちろん!
日焼け後のケアもとても大切です。
プロテクトエナジーは、日焼け後でも効果大!!
GWや運動会で焼けないようにしっかりと紫外線対策をしましょう。
人気商品のため、在庫切れの場合がございます。
お求めの際は、予めお問合せください。
093-621-0198 メディカルサーノスタッフまでお問合せください。
新年度になりました!
こんにちはSTです!
4月になり新たな年度が始まりましたね♪
浜田病院も前年度よりもより多くの方に慕ってもらえるような病院を目指して日々の業務に励んでおります!
リハビリテーション科も少数ながらに一致団結して頑張っております!
皆様、今年度も浜田病院を宜しくお願い致します♪
さて、前回は『リハビリテーション』についてお話をさせていただきました。
そして今回はリハビリの中でも『理学療法士(PT)』についてお話をさせてもらおうと思っております。
『理学療法士(Physical Therapist:PT)』とは
病気、けが、障害などにより運動機能が低下した状態にある人に対し、基本動作(寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行)の維持・改善を目的に運動、温熱、電気などのリハビリテーションを提供させて頂き、ADL(日常生活動作)の拡大、QOL(生活の質)の向上を図るセラピストのことです。
具体的には、ベッド・床上での訓練、平行棒や杖などを用いた歩行訓練、関節可動域訓練、筋力トレーニング、痛みの軽減に対する温熱や電気療法といった内容を実施しています。
簡単に説明すると
『立つ』『歩く』『座る』といった普段何気なく行っている動きが上手くできなくなった方に、動き方の練習またはアドバイスをしてくれる人』
といったところですかね♪
健康なときは特に意識しなくても起きたり、歩いたりできますが、実は一つ一つの運動には様々な筋肉が働いているんです!
もしも『立つ』『歩く』『座る』といった動作ができなくなってしまったら、いつも通りの生活を送ることはかなり難しくなってしまいます。
そんな時に、普段の生活を送れるように手助けをしてくれる存在が理学療法士というわけです!
当院では入院患者様の理学療法だけでなく外来患者様の理学療法も実施しています♪
スタッフも優しいスタッフとおもしろいスタッフしかおりませんのでお気軽に御来院もしくは御相談をお待ちしております!
それでは今月も張り切って頑張りましょう!
潮干狩りのシーズンですね。「貝毒」について知っておきましょう(*^ω^*)
こんにちはPhです。
今回は、実は恐ろしい貝毒についてお伝えします。
4~5月は潮干狩りのシーズンですね♪私も何度か子供と行き、とても楽しい思い出です。しかし、気をつけたいのがアサリ、ムラサキガイ、ホタテガイなどの二枚貝が持つ
「貝毒」(ノ゜⊿゜)ノ
貝毒といっても、二枚貝自身が毒素を作り出すわけではありません。光や水温などの環境変化によって有毒の植物プランクトンが発生すると、これを食べた二枚貝が毒素を蓄積し、その毒化した貝を食した人に食中毒をもたらすというものです。麻痺性の貝毒、下痢性の貝毒があります。
アメリカやニュージーランドでは、口内のしびれや運動失調などの障害を招く神経性の貝毒も発生するようです。
記憶喪失をもたらす恐ろしい貝毒も存在します。これもまた海外ですが、1987年に奇妙な食中毒が発生しました。ムラサキガイを食べた人たちに記憶喪失、痙攣、昏睡などの症状があらわれ、患者107人のうち3人が死亡したのです。調査の結果、植物プランクトンが作るドウモイ酸が毒素だと判明しました。
幸いなことに、1987年以降、記憶喪失性貝毒による食中毒は起きていませんが、こうした様々な貝毒が厄介なのは、毒化した貝を外見から見極めることはできず、一般的な調理加熱では毒素は分解しないという点です。日本では、麻痺性貝毒と下痢性貝毒について規制値があり、毒化した貝は市販されることはありません。しかし、潮干狩りで採った貝などは出荷規制の対象外です。なので、厚生労働省や自治体のホームページで調べることが大切です。
楽しい潮干狩りのためにも皆さん是非とも「貝毒情報」「貝毒検査結果」で検索してから出発してくださいね♪
待ちに待っていました!
こんにちはSTです。
今年の2月は例年と比較し寒い日が多くありましたね。雪もかなり降ったり、積もったり…。もう積雪にはこりごりです…。
しかし、3月に入ると気温も暖かくなり、急に春らしくなってきましたね!ようやく寒さを気にせず外に出ることができそうです♪
そんな話はさておき、皆様は『リハビリテーション』についてどの程度ご存知でしょうか?
『リハビリテーション』とは
【病気や怪我を患ってしまった方に対して社会復帰の支援や日常生活への復帰支援をサポートすること】
ちょっと難しいですかね?(笑)
少し具体的に言うと、骨折や脳血管障害(脳出血や脳梗塞など)などを患ってしまった方に対して、元の日常生活をおくることができるように運動のお手伝いやアドバイスしているのです。
それでは、リハビリテーションは3つの種類に分かれていることはご存知でしょうか?
リハビリテーションは
・理学療法士(Physical Therapist:PT)
・作業療法士(Occupational Therapist:OT)
・言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)
の3職種があります。
なぜ3つの種類があるかといいますと、担当する分野に違いがあるのです。
わかりやすく簡単に担当分野を説明すると、
・理学療法士(PT)
→体全体の大きな運動のリハビリを担当
・作業療法士(OT)
→体の中でも細かな運動や、注意散漫や記憶障害などのリハビリを担当
・言語聴覚士(ST)
→言語障害(失語症や構音障害)や摂食・嚥下障害(飲み込みの障害)のリハビリを担当
それぞれ専門分野を持つことで、より質の高いリハビリを提供できるようにしているのです♪
さて、次回は理学療法士が具体的にどのような方にどのようなリハビリを実施しているのかといった細かな内容をお伝えできればと思っております♪
それでは、また次回にご期待下さい♪
漢方薬をおいしく飲むコツ😋
こんにちはPhです。
今回は、漢方薬をおいしく上手に飲むコツをお伝えします。
本来の漢方薬は生薬を自分で煎じて、その湯液を飲むものでした。
ところが日本では、およそ60年前に、なんと!インスタントコーヒーにヒントを得て、漢方エキス製剤が生まれました。さらに日本の漢方製剤の品質は世界でも高い評価を得ているそうです。
ただ、残念ながら漢方薬はあまり美味しいとは言えません。量も多く、内服回数も3回が基本で、ストレスに感じる方もいるのではないでしょうか?
そこで!!おいしく上手に飲むコツです!
☆湯に溶かす☆
50ml程度のお湯に溶いて(完全には溶けませんが
顆粒は口の中にいつまでも残って味がしますが、液体だと、一瞬で喉元を過ぎ去るということのようです。
☆甘みをつける☆
ハチミツなどで甘みを付けて飲みます(1歳以上)。
☆ココアやコーヒー☆
逆に苦いものと飲むと苦にならないということのようです。
★花粉症対策★
こんにちはみなさん、MedicalSa-noスタッフの岡です。
春の訪れが待ち遠しいですがいかがお過ごしでしょうか。
暖かい春と一緒にやって来るのが花粉です!!(ノ゜⊿゜)ノ
花粉症の方はこの時期は本当に辛いですよね。
ということで今回は花粉症対策について少しお話しいたします。
■粘膜がダメージを受けると症状が悪化します!
鼻や口、器官は外敵から体を守るために、粘膜で覆われています。
粘膜に花粉やホコリなどが付着すると、それを体外へ排出しようとして
鼻水や咳、くしゃみなどが出ます。
花粉やホコリがたくさん侵入してしまうと症状は悪化します。
またストレスがあると免疫機能の機能が低下してしまい、症状を悪化させる要因とされています。
花粉症の症状を和らげるためには
★粘膜を強くする
★免疫力向上
★腸内環境を整える
ということが必須となります。特に腸内環境を整えることはとても重要です。
腸内には多くの免疫細胞が存在するため、腸内環境を整えることで免疫力を正常に保ち、アレルギー症状を緩和できる働きをします。
逆に花粉症対策として控えた方がいいものは、腸内環境を悪化させる要因となる
脂肪分が多い肉の摂りすぎや、お菓子やジュースなどの甘いものの摂りすぎ、
コーヒーなどの刺激物、油げものや過度の飲酒などは、炎症を悪化させる要因となるので注意が必要です。
アレルギー体質の改善、免疫バランスの正常化、そして抗ストレスが花粉症の症状を
和らげる働きをするということが大切です。
花粉症を食事やサプリメントで完全に完治することは難しいですが、緩和することは可能です。
食事対策は花粉症の季節だけでなく、年間を通じて行うことが大切です。
また、単一の食材を食べたからといって花粉症が良くなるわけではありません。
まずは主食、主菜、副菜の揃った栄養バランスが整った食事を毎日摂る事を心がけましょう。
当院では粘膜を強くし免疫力向上に働くサプリメントや、腸内環境をサポートする
サプリメントもご用意しております。また、アレルギー検査なども行っております。
詳しくはMedical Sa-noスタッフまでお問合せください。
それでは今年も花粉に負けないように頑張りましょう!!